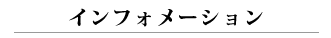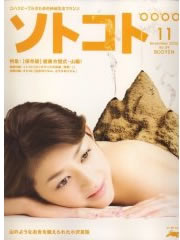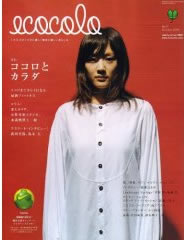ネイチャー&サイエンスカフェ Vol.2『わらの家から住まいと暮らしを見直す ~失われつつあるつながりを取り戻すために~』

11 月27日(月)、東京渋谷にあるモンベルクラブ5Fのサロンで行われた「ネイチャー&サイエンスカフェ Vol.2」でスローデザイン研究会世話人の大岩剛一が講演をしました。伊藤信子さんの司会に始まり、大岩は80点もの里山やわらの家の写真をもとに、自 身の子供時代の原風景から現在の都市の姿、その在るべき姿を語り問いかけます。
大学生から専門家まで、年齢もまちまちの参加者の方々から、自己紹介と同時に多くの質問がとび出し、最後は異例の二次会にまで発展するという、積極的なディスカッションの場になりました。
家やまちに関わるひとりひとりの心の原風景を掘り起こし大切にしていくことが、未来の私たちの暮らしを豊かなものにしていく。今回の講演から、私自身も強 くそのことを再確認させられ、自身に問いかけなおす良い機会となりました。
(報告:上村彩果)
【日時】
11月27日(月) 18時00分開場18時半~20時
【場所】
モンベルクラブ渋谷店5Fサロン(03-5784-4005)
東京都渋谷区宇田川町11番5号モンベル渋谷ビル
【主催】
伊藤企画・伊藤信子